タイガー炊飯器の購入や買い替えを検討している中で、「極うまモード」と「白米モード」の違いが気になっている方も多いのではないでしょうか。とくに「タイガー炊飯器 極うま 違い」と検索している方にとっては、具体的に何がどう異なるのか、使い勝手や炊き上がりの仕上がりにどんな変化があるのかをしっかりと理解しておきたいところです。
この記事では、極うまメニューは何を目指した機能かをはじめ、極うまと白米モードの違いを比較しながら、極うまの吸水工程はどんな特徴があるのか、また極うまの炊き時間はどれくらいかかるのかといった疑問に丁寧に答えていきます。
さらに、極うまで炊いたご飯の特徴とは何か、極うまモードで使う水の量の目安とはどの程度か、極うまで予約炊飯するときの注意点にも触れながら、極うまを使った炊き方の基本操作もわかりやすく解説。
電気代への影響や、極うまに向いているお米の種類と特徴も併せて紹介することで、「極うま」モードを最大限に活用するためのポイントを網羅的にお届けします。炊飯器選びや日々のごはん作りに役立つ情報を求めている方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
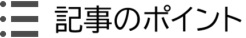
- 極うまモードが目指している炊飯の美味しさと特徴
- 白米モードとの工程や炊き上がりの違い
- 吸水時間や水の量など極うま特有の炊き方
- 極うまモードが適しているお米の種類や使い方
関連記事
タイガー炊飯器の極うまと白米の違いとは

おうち家電ラボ・イメージ
- 極うまメニューは何を目指した機能か
- 極うまと白米モードの違いを比較
- 極うまの吸水工程はどんな特徴があるのか
- 極うまの炊き時間はどれくらいかかるのか
- 極うまで炊いたご飯の特徴とは
極うまメニューは何を目指した機能か

おうち家電ラボ・イメージ
タイガー炊飯器に搭載されている「極うま」メニューは、その名の通り「ごはんを極限まで美味しく炊き上げること」を目的とした高機能な炊飯プログラムです。特別な日や、普段使いでも一段上の味を楽しみたいというユーザーのニーズに応えるよう設計されています。
このモードの開発背景には、土鍋炊きのような“本物の美味しさ”を家庭で簡単に再現したいというタイガーの技術的挑戦があります。従来の「白米」モードとは異なり、「極うま」はお米の芯までしっかりと水分を浸透させるため、炊飯プロセス全体で時間をかけ、丁寧に熱を加える設計となっています。
具体的には、炊飯の前段階である「吸水」に時間をたっぷりかけて、お米がゆっくりと水を吸収するようにし、その後も火力や温度の上げ下げを細かく調整しながら加熱します。この工程によって、米の甘みや粘り、弾力といった“おいしさの本質”を最大限に引き出すのが極うまの狙いです。
以下に、「極うま」が目指している機能のポイントを分かりやすくまとめた表を掲載します。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 吸水時間 | 白米モードの約2倍。ゆっくりと米に水を染み込ませる設計 |
| 加熱工程 | 土鍋炊飯を参考に、緩やかな立ち上げと強火のコンビネーションで旨みを引き出す |
| 狙う味わい | 米本来の甘み・香り・粘り・弾力を最大限に引き出す |
| 対応する機種の幅広さ | IH式から土鍋圧力IHまでさまざまなモデルで対応 |
| 使用シーン | 特別な日や高品質なお米を楽しむ時に最適 |
つまり、「極うま」はただの高級モードではなく、タイガーの技術と炊飯哲学が凝縮された“美味しさの最大化”を追求する一つの答えと言えるでしょう。日常のごはんにちょっとした贅沢をプラスしたいときにこそ、活用する価値があります。
極うまと白米モードの違いを比較

おうち家電ラボ・イメージ
タイガー炊飯器には「白米」モードという基本的な炊飯機能がありますが、「極うま」モードはその上位に位置する特別メニューとして設定されています。どちらも美味しいごはんを炊くためのモードですが、目的や工程、仕上がりに大きな違いがあります。
まず注目すべきは、「炊飯プロセスの設計思想」です。「白米」モードは、安定した炊き上がりを重視しており、日常的に手軽に使えることが優先されています。一方の「極うま」は、“おいしさを極める”ことを目的としており、あえて時間をかけてお米の旨みを丁寧に引き出すよう設計されています。
次に、具体的な違いとして現れるのが「吸水時間と炊飯時間」です。「白米」は平均して40~50分で炊き上がりますが、「極うま」モードでは55~70分ほどかかるのが一般的。これは、時間をかけてじっくり吸水させる工程が含まれているためです。この長い吸水が、甘みや香りを引き出す鍵となります。
炊きあがりのご飯の食感にも明確な差があります。「白米」はバランス型の食感で、誰にでも合うように設計されています。一方、「極うま」で炊いたご飯は、粘りや弾力が強く、やわらかめで“もちっとした”仕上がりになる傾向があります。これにより、お米そのものの甘さや風味をダイレクトに感じやすくなっています。
この違いは、どちらが優れているというよりも「用途」や「好み」によって選び分けるのが正解です。例えば、急いでいる朝や忙しい平日は「白米」、ゆっくり味わいたい夕食や来客時には「極うま」といったように、シーンごとの使い分けが効果的です。
「極うま」と「白米」は、単なる名前の違いではなく、“炊き方の思想”から異なるモードです。それぞれの特性を理解することで、日々の食事の満足度が大きく変わるでしょう。
極うまの吸水工程はどんな特徴があるのか

おうち家電ラボ・イメージ
「極うま」モードにおいて、最も特徴的で味の決め手になる工程が「吸水」です。一般的な炊飯モードよりも、はるかに長い時間をかけて米に水を浸透させるこの工程は、タイガー独自の技術力と“ごはんの美味しさ”に対する強いこだわりの表れでもあります。
炊飯において吸水とは、お米が水を取り込み、炊飯中の加熱でしっかりと膨らみ、柔らかくなるための準備段階です。「極うま」モードではこの吸水工程に通常の白米モードの約2倍の時間をかけて、じっくりと水を米の芯まで届けます。こうすることで、米の内部にまで均等に水が浸透し、炊き上がりにムラが出にくくなります。
さらに、吸水が深くしっかり行われることで、加熱中のデンプンの糊化(α化)がスムーズになり、粘りと弾力のあるふっくらした仕上がりになります。これによって、ごはん本来の甘みや香りも引き立つため、おかずがなくても満足できる味に近づけるのです。
また、「極うま」モードの吸水は単に“時間を延ばしただけ”ではありません。温度制御も細かく調整されており、お米の状態に合わせて最適なタイミングで水を吸わせるよう設計されています。これにより、水温が低すぎたり高すぎたりして米に負担をかけることなく、自然に、ゆっくりと吸水が進行します。
以下に、「極うま」の吸水工程と通常モードの違いを表にまとめました。
| 吸水工程の違い | 極うまモード | 白米モード |
|---|---|---|
| 吸水時間 | 長め(白米モードの約2倍) | 標準的な時間 |
| 吸水の目的 | 甘み・粘り・弾力を最大限に引き出す | バランスのとれた仕上がりを目指す |
| 吸水方法の温度管理 | 細かく調整しながら吸水を促進 | 比較的シンプルな温度制御 |
| 吸水の深さ | 米の芯までしっかり水を届ける | 表層から内部へ標準的に吸収される |
| 吸水後の炊き上がりへの影響 | もっちり・ふっくら、風味豊かなごはんに | 標準的な食感と味わい |
このように、「極うま」モードの吸水工程は、タイガーの炊飯技術の中でも中核をなす重要なプロセスです。米の本質的な美味しさを引き出すために、時間と丁寧な熱コントロールをかけて設計されているのです。
極うまの炊き時間はどれくらいかかるのか

おうち家電ラボ・イメージ
「極うま」モードを使う際に気になるポイントの一つが、炊き上がりまでの時間です。通常の「白米」モードと比べてどの程度長くなるのか、どんな影響があるのかを知っておくことは、実際の食事準備の計画にも直結します。
炊飯時間は使用する炊飯器の機種やお米の量によっても前後しますが、「極うま」モードではおおむね 55分から70分 程度かかるのが一般的です。一方で、標準的な「白米」モードでは 35分から50分前後 で炊きあがるケースが多いため、平均して 10〜20分ほど長くなることがわかります。
この時間の差は、単に炊飯がゆっくり行われるというより、前工程の「吸水」に時間をかけているからです。「極うま」では、炊飯器がスタートしてすぐに加熱を始めるわけではなく、まずじっくりと米に水を吸わせ、内部まで水分を行き渡らせてから、次に進む構成となっています。
炊飯時間が長いことはデメリットにも感じられますが、裏を返せば「時間をかけた分だけ味わいが深くなる」ことを意味します。実際、多くのレビューや公式資料でも、炊飯時間の長さがごはんの甘みや弾力、香りに好影響を与えていると評価されています。
このモードを使用する際は、時間に余裕のあるときに活用するのがおすすめです。例えば、休日の昼食や夕食、または予約炊飯を活用して朝に炊き上がるようセットしておけば、待ち時間を気にせずに極上のごはんを楽しむことができます。
まとめると、「極うま」は確かに炊飯に時間はかかりますが、その分得られる味と食感のクオリティは高く、日常の食事をより豊かにする価値のあるモードです。急いでいるときは白米、時間をかけられるときは極うまと、使い分けることで満足度の高い炊飯生活が実現できます。
極うまで炊いたご飯の特徴とは

おうち家電ラボ・イメージ
「極うま」モードで炊いたごはんは、通常の「白米」モードで炊くごはんとは一線を画す味と食感を目指して設計されています。その最大の特徴は、“お米のポテンシャルを最大限に引き出す”というコンセプトにあります。甘み・粘り・弾力・香りといった要素が際立ち、まるで高級料亭で出てくるような「ごはんそのものを主役にできる一膳」を目指しています。
炊き上がりのごはんは、噛んだ瞬間にほんのりと甘みが広がり、もちもちとした弾力が感じられるのが特徴です。長時間の吸水によって、米粒の芯までしっかりと水分が行き渡っており、それがふっくら感につながっています。また、蒸らしを丁寧に行う工程があるため、全体的にムラの少ない、均一で安定感のある炊き上がりになります。
一方で、「やや柔らかめ」と感じるユーザーもいるようです。これは吸水時間が長いぶん、水分量が多く米の粒がふっくらと仕上がるためで、特に硬めのごはんを好む方にとっては少しソフトに感じられるかもしれません。逆に、やさしい口当たりのごはんが好きな方には非常にマッチする炊き上がりです。
また、冷めても甘みや粘りが残るという特徴も見逃せません。おにぎりやお弁当にも向いており、再加熱しても比較的風味が落ちにくいのもポイントです。
以下に、「極うま」で炊いたごはんの特徴を表にまとめました。
| 特徴分類 | 内容 |
|---|---|
| 味わい | 甘みと旨みが強調される。塩むすびだけでも満足できるレベルの濃さ |
| 食感 | もちもち、弾力あり。やわらかめに炊き上がる傾向 |
| 粒立ち | ふっくら炊きあがるが、柔らかめゆえに粒感がやや弱くなる場合も |
| 香り | 蒸らし工程により、炊きたて時に香り立ちがよく、土鍋に近い炊き上がり |
| 冷めたときの美味しさ | 冷めても甘み・粘りが持続しやすく、おにぎりなどにも向く |
| 好みによる評価 | 柔らかめのごはんを好む人に最適。一方、硬め派には水加減調整が必要な場合も |
このように「極うま」モードは、お米の魅力を最大限に活かしたごはんを炊くために設計されています。好みやシーンに合わせて活用すれば、普段の食事が一段と贅沢なものになるはずです。
関連記事
タイガー炊飯器 極うまの使い方と注意点
- 極うまモードで使う水の量の目安とは
- 極うまで予約炊飯するときの注意点
- 極うまを使った炊き方の基本操作
- 極うまは電気代にどれほど影響するのか
- 極うまに向いているお米の種類と特徴
極うまモードで使う水の量の目安とは

おうち家電ラボ・イメージ
「極うま」モードを使ううえで、水の量の調整は炊き上がりの食感や味に大きな影響を与える重要なポイントです。多くのタイガー炊飯器には「極うま」専用の水位線が内なべに記載されており、その線に合わせて水を入れるのが基本的な目安となります。
もし「極うま」の水位線がない機種を使っている場合は、まず「白米」モードの水位線を基準に設定するのが無難です。ただし、「極うま」は長時間の吸水によってごはんが柔らかくなりやすいため、白米と同じ水量で炊くと、想定よりも柔らかいごはんになることがあります。これが「柔らかすぎる」と感じる一因になっているケースも多いです。
そのため、硬めのごはんを好む人は、最初は白米の水位線よりもほんの少し少なめに水を入れて炊き、そこからお好みに合わせて微調整していくのがおすすめです。逆に、やわらかめでも構わない、あるいはそれを好む方は白米の線か、やや多めでも問題ありません。
また、炊飯量によっても仕上がりに影響が出ます。1合だけの少量炊きの場合、水の量が少ない分、吸水と加熱のバランスが崩れやすくなり、ベタつきやすくなる傾向があります。そのため、少量を炊く際は特に水加減を慎重に行う必要があります。
水の量を正確に計るためには、計量カップと水位線の目視確認が大切です。また、米の状態(新米かどうか、保管状態など)によっても適正な水の量は変化します。新米は水分を多く含むため、やや控えめにするのが基本とされています。
つまり、「極うま」モードの水量設定は、取扱説明書と内なべの目盛りを基本にしつつ、ご自身の好みやお米の種類によって微調整していくことが最適な炊き上がりを得るためのポイントとなります。時間をかけて吸水し、しっかりと加熱される「極うま」だからこそ、水の量が味と食感に直結することを意識して使うようにしましょう。
極うまで予約炊飯するときの注意点

おうち家電ラボ・イメージ
「極うま」モードを使って予約炊飯を行う場合は、通常の「白米」モードよりも時間や設定に注意が必要です。このモードは炊飯工程において長時間の吸水と丁寧な加熱を行うため、予約設定の際にもそれに合わせた準備が求められます。
まず確認すべきなのは、「極うま」モードが予約炊飯に対応しているかどうかです。ほとんどのタイガー炊飯器では「極うま」も予約対応していますが、一部の機種では対応していない場合や、予約設定できる最短時間が通常モードよりも長く設定されていることがあります。たとえば、予約は「1時間30分以上先」でないと受付できないといった制限がある機種もあります。
また、炊飯時間が長くなるという特性上、炊き上がりの時刻から逆算して早めに予約を設定する必要があります。仮に「白米」モードが約50分で炊き上がるのに対し、「極うま」モードでは60分〜70分程度かかる場合があり、予約時間の設定を誤ると「食事の時間に炊き上がっていない」という事態も起こり得ます。
加えて、水加減にも注意が必要です。長時間の吸水工程によって、お米がより多くの水を含むため、白米モードと同じ水量でセットしてしまうと、柔らかすぎる炊き上がりになることがあります。予約炊飯の際は、事前に自分の好みに合った水量を把握しておき、その量を正確に量ってセットすることが重要です。
さらに、長時間放置されることを前提とする予約炊飯では、衛生面への配慮も欠かせません。特に夏場など気温が高い時期には、お米を長時間水に浸したままにしておくと、雑菌が繁殖するリスクがあります。予約時間が長くなる場合は、冷蔵庫で冷やした水を使う、あるいは予約自体を避けるといった対策をとると安心です。
以下に、予約炊飯を行う際に押さえておきたいポイントを表にまとめました。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 予約可能時間の確認 | 「極うま」では予約可能な最短時間が制限されている機種もある |
| 必要な炊飯時間 | 白米より長いため、炊き上がり希望時間から十分に逆算してセットする |
| 水加減 | 柔らかめに炊き上がる傾向があるため、白米よりやや少なめが目安 |
| 衛生対策(特に夏場) | 冷水を使う・長時間放置を避けるなど、雑菌繁殖を防ぐ工夫が必要 |
| お米と水の事前準備 | 炊飯直前と同じように計量・洗米し、セット後は炊飯器を動かさないようにする |
これらのポイントを踏まえておけば、「極うま」モードでも快適に予約炊飯を活用することができます。特に時間のコントロールと水量調整は仕上がりを左右する重要な要素なので、しっかり確認してからセットすることをおすすめします。
極うまを使った炊き方の基本操作

おうち家電ラボ・イメージ
「極うま」モードを使ってごはんを炊くための操作は、特別に難しい手順があるわけではありません。タイガー炊飯器の設計は、初めて使う人でも直感的に操作しやすいよう工夫されており、操作パネルのボタンもシンプルにまとめられています。以下では、極うまモードでの炊飯手順を順を追って紹介します。
まず最初に行うのは、基本的な準備です。お米を計量カップで必要な分量だけ量り、水で丁寧に研ぎます。このとき、研ぎ終わったお米をすぐに炊飯器の内釜に入れて、定められた水位線まで水を注ぎます。極うま専用の水位線がある場合は、それに合わせるのがベストです。専用の線がない場合は、白米用の水位線を参考にしながら、お好みで微調整します。
次に、炊飯器の電源を入れ、メニュー選択ボタンから「極うま」モードを選びます。多くのモデルでは、ボタンを何度か押してメニューを切り替え、「極うま」の表示が出たら決定ボタンを押す仕様になっています。モード選択後、「炊飯」ボタンを押せば、炊飯がスタートします。
炊飯開始後は、液晶画面に炊き上がりまでの時間が表示されるモデルもありますが、「極うま」モードでは吸水時間が長いため、炊き始めてしばらくは残り時間が表示されないこともあります。これは異常ではなく、吸水が十分に終わった段階で、初めて時間表示が始まる仕組みです。
また、炊き上がりまでの時間は通常よりも長く、機種によって異なりますが、55〜70分ほどかかるのが一般的です。夕食や弁当の準備に使う場合は、余裕を持って炊飯を開始するようにしましょう。
炊き上がり後は、蒸らし時間も含めてしばらく待ちます。タイガー炊飯器の多くは自動で蒸らし工程が組み込まれており、炊飯完了のアラームが鳴ったらすぐに蓋を開ける必要はありません。5〜10分ほどそのまま置いておくと、ごはん全体がよりふっくらと整います。
最後に、しゃもじでごはんをほぐして全体を均一に混ぜましょう。これにより、余分な水分が飛び、粒立ちのよいごはんになります。
このように、「極うま」モードは基本的な炊飯操作と大きく変わる点は少ないものの、丁寧な準備と時間に余裕を持ったスケジューリングが重要になります。手間をかけたぶんだけ、しっかりと美味しさが返ってくるのが「極うま」モードの魅力です。
極うまは電気代にどれほど影響するのか

おうち家電ラボ・イメージ
「極うま」モードは、美味しさを追求するために吸水や加熱の工程に多くの時間をかける設計になっており、炊飯プロセス全体の所要時間が長くなる点が大きな特徴です。そのため、当然ながら電気の使用時間も増え、標準モードに比べると電気代が高くなる傾向があります。ただし、その差は思っているほど大きな負担にはならないケースがほとんどです。
電気代に影響する要素としては、まず「炊飯時間の長さ」が挙げられます。白米モードが約45〜55分で炊けるのに対し、極うまモードではおよそ60〜70分と、10〜20分程度長くかかります。この時間の差が、加熱にかかるエネルギー量の差に直結します。
実際に、炊飯器の消費電力は多くのモデルで1,000W前後とされており、炊飯時にはそれに近い電力が継続して使用されます。仮に白米モードで1時間あたり約27円、極うまモードで1.3倍の時間がかかるとすると、単純計算で1回あたり3〜5円ほどの電気代差が出ることになります(契約電力会社やプランにより異なります)。
さらに注目すべきなのは、「エコ炊きモード」や「早炊きモード」との差です。これらのモードは加熱時間や温度調整を最適化することで、白米モードと比較しても電気代を約10〜30%抑えることができるよう設計されています。したがって、極うまモードとエコ炊きモードを比べると、電気代の差はより明確になります。
以下に、各炊飯モードの消費電力と電気代の目安を比較した表を掲載します。
| モード名 | 炊飯時間(目安) | 消費電力(W) | 電気代(1回あたり) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 白米モード | 約45〜55分 | 約1,000W | 約20〜25円 | 標準的な味と硬さのバランス |
| 極うまモード | 約60〜70分 | 約1,000W | 約25〜30円 | 味と食感を引き出すため時間と電力を多く使う |
| エコ炊きモード | 約40〜50分 | 約800W前後 | 約15〜20円 | 省エネ設計でやや硬めの仕上がり |
| 早炊きモード | 約25〜30分 | 約900W前後 | 約10〜15円 | 時短優先でやや固めのごはん |
このように、「極うま」は味のクオリティと引き換えに多少の電力コストをかけるプレミアムモードです。とはいえ、1回あたり数円〜十円程度の違いであり、家庭の電気代全体に大きな影響を与えるほどではありません。「今日は特別に美味しいごはんを食べたい」と思った日だけ極うまモードを選ぶなど、用途を絞って使うことで、費用対効果の高い選択ができます。
極うまに向いているお米の種類と特徴

おうち家電ラボ・イメージ
タイガー炊飯器の「極うま」モードは、甘み・うまみ・粘り・弾力といったお米の持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出すことを目的として設計されています。そのため、どんなお米でも使える一方で、特にこのモードの特性と相性が良いとされるお米の種類があります。
極うまモードでは、吸水時間が長く設定されており、芯までしっかり水を含ませることにより、加熱時にでんぷんがよく糊化し、もちもちとした食感に仕上がるのが特徴です。したがって、もともと粘りや甘みのあるお米、あるいは新鮮で水分を多く含む「新米」などは、極うまモードの恩恵をより強く感じることができます。
具体的には、以下のようなお米が極うまモードに向いています。
- ひとめぼれ:バランスの取れた甘みと粘りがあり、柔らかくふっくらとした炊き上がりが魅力。
- ゆめぴりか:強い粘りとコクがあり、冷めてもおいしい。極うまでさらに風味が引き立つ。
- コシヒカリ:日本を代表する銘柄米で、甘み・粘り・香りの三拍子がそろう。極うまとの相性も良好。
- つや姫:粒立ちの良さと上品な甘みを持ち、モードによって味の差がはっきり感じられる品種。
一方、硬めの食感が好まれるお米(例:あきたこまち)や、吸水によって柔らかくなりすぎる傾向のある古米などは、極うまモードではやや過剰に柔らかくなることもあるため、水の量を調整するか、標準の白米モードを使うほうが無難です。
また、雑穀米や玄米は、極うまモードではなく、それぞれの専用モードで炊くことが推奨されます。これらの穀物は吸水時間や加熱時間の最適値が異なるため、極うまで炊くと硬かったり、逆にベタついたりする可能性があります。
このように、「極うま」モードに向いているお米は、もともと甘みや粘りの強い品種が中心です。特にお米そのものの味をしっかり楽しみたい場合は、極うまモードと高品質な白米の組み合わせが最大の効果を発揮します。炊き込みごはんなどの味付き料理ではなく、まずは白ごはんでその炊き上がりをじっくり味わってみるのがオススメです。
関連記事
総括:タイガー炊飯器で極うまモードを選ぶ理由と白米モードとの違い
記事をまとめました。
- 極うまモードはごはんの美味しさを最大化するために設計された
- 吸水時間が白米モードの約2倍と長く設定されている
- 加熱工程において火力の緩急をつけて旨みを引き出している
- 土鍋炊きのような風味と食感を目指した設計思想である
- 炊飯時間は55〜70分と白米モードより長い
- 炊きあがりのごはんは粘りと弾力が強くやわらかい仕上がり
- 吸水工程では米の芯まで均等に水を行き渡らせる工夫がある
- 冷めても甘みや粘りが持続し、おにぎりや弁当にも適している
- 水の量は専用水位線を基準に微調整するのが望ましい
- 硬めが好みの場合は白米水位よりやや少なめが推奨される
- 予約炊飯では衛生面や炊飯時間の逆算設定が必要になる
- 操作はシンプルで通常の炊飯と手順に大きな違いはない
- 電気代は白米モードよりやや高めだが数円程度の差に収まる
- 甘みや粘りが強い銘柄米(ひとめぼれ、ゆめぴりか等)と相性が良い
- 白米モードは日常使い、極うまは特別な日のごはんに向いている








